

個人情報の保護
診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ
当院は、患者さんへの説明と同意に基づく診療(インフォームド・コンセント)および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
【診療情報の提供】
- ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、担当医師または看護師に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。
【診療情報の開示】
- ご自身の診療記録の閲覧や複写の交付をご希望の場合は、遠慮なく、相談窓口に開示をお申し出ください。開示・複写の交付に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。
【プライバシーについて】
- 確認等で緊急性を認めた内容について、患者ご本人・ご自宅・勤務先に連絡する場合があります。連絡先のご希望がある場合は、相談窓口へお申し出ください。
- 外来で患者を診察室に案内する際等、誤認がないように氏名をお呼びします。また、患者ご本人の確認のために、フルネームで名乗っていただきますので、ご協力をお願いします。
- 外来等での氏名の呼び出しについて望まない場合、中央受付にお話しください。
- 院内一斉放送は、緊急時以外行いません。
- 病室入り口やベッドのネーム表示は、患者取り違え防止、自分の部屋の所在確認の目的で行っています。
- 病室における氏名の掲示を望まない場合、面会者からの問い合わせ、電話の取次ぎを望まない場合には、病棟看護師にお話しください。
個人情報保護方針
当院は信頼の医療に向けて、患者に良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。患者の個人情報につきましても、適切に保護し、管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
【個人情報の確認・内容訂正・利用停止】
- 個人情報とは、氏名、住所等の特定個人を識別できる情報を言います。
- 患者の個人情報について患者が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、適切に対応いたします。また、当院が保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。相談窓口にお申し出ください。調査の上、対応いたします。
【個人情報の収集について】
- 個人情報を収集する場合、診療・看護および患者の医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を収集する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。
【個人情報の利用及び提供について】
- 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
〇患者の了解を得た場合
〇個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
〇法令等により提供を要求された場合 - 当院は、法令の定める場合等を除き、患者の許可なく、その情報を第三者に提供いたしません。
【個人情報の適正管理について】
- 患者の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
【法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善】
- 個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
【相談窓口】
- ご質問やご相談は、各部署責任者または中央受付総務課(個人情報保護相談窓口)でお受けいたします。
2022(令和4)年8月 公立七日市病院 院長
当院における個人情報の利用目的の範囲
【医療提供】
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者への医療提供に関する利用
【診療費請求のための事務】
- 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関又は保険者への照会
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答、その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
【当院の管理運営業務】
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さんの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
【上記以外】
- 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
- 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内において行われる医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
- 外部監査機関への情報提供
- がん登録、取得及び利用(第三者機関への情報提供を含む)
【付記】
- 診療のために利用する他、病院運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による病院評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。また、研修・養成の目的で、研修医および医療専門職の学生等が、診療、看護、処置などに同席する場合があります。
- 上記の利用目的について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
- これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
医療安全管理指針
安全管理指針の目的
この指針は、医療事故をはじめとする病院危機の予防・再発防止・発生時の適切な対応など公立七日市病院における医療安全体制を確立し、適切で安全な質の高い医療の提供を目的とする。
医療安全管理に関する基本的な考え方
医療安全の基本は、医療事故を起こした個人の責任を追及するのではなく、医療事故を発生させた安全管理システムなどの不備や問題点に注目し、それらの根本原因を究明し改善していくことである。
職員は医療事故を起こさないという信念のもとに、患者に信頼される医療の提供と医療の質の向上に努力し、安全な患者中心の医療を提供する。基本姿勢を基に、医療安全の必要性・重要性を全職員に周知徹底し、院内全体で医療安全を積極的に行う。
組織及び体制
(1)医療安全管理委員会
医療安全に関し必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資するため、医療安全管理委員会を設置する。
本委員会は別に定める公立七日市病院医療安全管理委員会設置要綱(内規)により活動する。
(2)医療安全管理室
組織横断的に院内の安全管理業務に関する企画立案、評価及び医療安全に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行うために医療安全管理部門(以下「医療安全管理室」という。)を設置する。
本部門は別に定める公立七日市病院医療安全管部門業務指針により活動する。
(3)リスクマネジメント部会
医療安全管理委員会や医療安全管理室と連携し、院内における医療安全対策の推進を目的として活動するために、リスクマネジャー部会を設置する。
リスクマネジャーは各職場で発生した事故・ヒヤリハットの全内容を把握し、分析・改善・対策をたて医療事故の減少に資するために活動する。
(4)医療安全管理者の配置
医療安全管理室に、専任の医療安全管理者を置く。
医療安全管理者は、医療安全対策に係る適切な研修を終了した専任の医師、薬剤師、看護師、その他の医療有資格者である。
・医療安全管理者は院長からの指示を受け、医療安全管理委員会と連携し、医療安全対策を行う責任と権限を有するものとする。
(5)医薬品安全管理責任者の配置
医薬品の安全使用を推進するため、医療安全管理委員会の下部組織として、医薬品の安全使用のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を置く。
・医薬品安全管理責任者は、薬剤部室長とし、医療安全管理委員会の連携の下、実施体制を確保するものとする。
(6)医療機器安全管理責任者の配置
医療機器の安全管理を推進するため、医療安全管理委員会の下部組織として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を置く。
・医療機器安全管理責任者は、副院長とし、医療安全管理委員会の連携の下、実施体制を確保するものとする。
(7)診療放射線安全管理者の配置
診療放射線に係わる安全管理のため、医療安全管理委員会の下部組織として、放射線の利用に関わる安全な管理のための責任者(以下「医療放射線安全管理者」という)を置く。
・医療放射線安全管理者は医師もしくは診療放射線科技師とし、医療安全管理委員会の連携の下、実施体制を確保するものとする。
医療安全管理のための研修
(1)医療安全管理のための研修の実施
医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画にしたがい、概ね6ヵ月に1回、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
(2)医療安全管理のための研修の実施方法
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聰しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
医療に係る安全確保を目的とした改善方策
(1)安全管理のためのマニュアルの整備
安全管理のため、本院において以下のマニュアルを整備する。
- ① 医療安全管理・医療事故等対応マニュアル
- ② 医療事故防止マニュアル
- ③ 医薬品安全管理マニュアル(医薬品の安全使用のための業務に関する手順書)
- ④ 医療機器安全管理マニュアル(医療機器の安全使用のための業務に関する手順書)
- ⑤ 感染対策マニュアル
- ⑥ 輸血マニュアル
- ⑦ その他
(2)医療事故防止マニュアルの作成と見直し
- ① 上記のマニュアルは、関係部署の共通のものとして整備する。
- ② マニュアルは、関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。
- ③ マニュアルは、作成、改変のつど、医療安全管理委員会に報告する。
(3)医療事故防止マニュアル作成の基本的な考え方
医療事故防止マニュアルの作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、医療事故防止マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。
また、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員がその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。
(4)医療安全報告制度の徹底
医療事故(インシデント・アクシデント)発生時、及び事故につながる可能性が認められる事例(ヒヤリ・ハット)について、医療安全報告(速報・続報)体制が整備されているが、従来医師からの報告が少ない等の問題があり、各部署での経験を病院全体で共有すべきであるという観点に立ち、報告制度の徹底を図ることが必要である。
事故を発見した職員は、上司への報告を行う。緊急を要する場合は直ちに口頭で報告を行い、その後速やかに事例に直接関与した当事者、もしくは発見者等が文書による報告を行う。
院長、および医療安全管理委員会の委員は、報告された事例について職務上知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。
報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
医療事故発生時の対応
「医療事故発生時の対応」に沿って対応する。
医療安全管理指針の閲覧
本指針は、公立七日市病院イントラネットに掲載するとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
医療安全対策に係る相談
相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に応じる為の支援をする。
職員からの情報提供に対応
医療安全に疑義が生じた場合、情報提供者が不利益なく情報提供できるよう医療安全ポストを設置する。
守秘義務
事故ヒヤリハット報告書や情報収集によって集めた情報については、医療安全管理対策に使用するものであり、他の目的には使用しない。データ処理後は速やかに処理する。
その他
本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、医療安全管理委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。
院内感染対策指針
院内感染に関する基本的な考え方
当院は患者中心の医療を基本理念とし、良質で安全な医療を提供する為、院内感染対策を重要と考えています。感染症の発生を未然に防止し、発生した感染症を広げない為に速やかに原因を究明し、終息させることが重要と考えます。全職員が院内感染防止対策を把握し、病院理念に則った医療の提供を実現します。
院内感染対策に関する組織
(1)感染対策委員会
当院で発生する感染症に関する組織的対策及び予防に関して必要な事項を協議するため、院長を委員長とし、関係各部門責任者及びその他の構成員からなる感染対策委員会を設置する。
(2)感染制御チーム(ICT)
(3)院内感染対策の充実と感染制御体制強化のため、感染制御チーム(ICT)を設置する。感染制御チーム(ICT)は以下の業務を行う。
- ① 職員の感染対策研修に関すること
- ② 感染対策マニュアルの作成・周知に関すること
- ③ 抗菌薬の適正使用に関すること
- ④ 院内感染発生状況に関すること
- ⑤ 職業感染防止に関すること
職員研修に関する基本方針
(1)全職員対象に、年2回、感染対策に関する研修会を実施する。
(2)新規採用職員に対しての講習を入職時に行う。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
(1)細菌検査から検出状況を把握し、毎月開催される感染対策委員会に報告する。
(2)感染対策委員会は、必要に応じて感染対策の周知や指導を行う。
(3)院内LANで感染情報レポートを配信し、注意喚起する。
院内感染発生時の対応に関する基本方針
(1)院内感染を生じ得る細菌が検出された場合、または感染症が発症した場合や疑われる場合は、主治医・看護マネジャーはICTに報告する。
(2)院内感染発生時には院長に報告し、各部署へ迅速かつ的確に情報を伝達する。必要に応じて感染対策委員会を開催し、原因の究明、改善策の立案・実行を行う。
(3)報告が義務付けられている感染症が特定された場合には、速やかに保健福祉事務所に報告する。
医療機関間の連携に関する基本方針
(1)緊急時に地域の医療機関同士が連携し、各医療機関のアウトブレイクについて相互支援がなされるよう、日常的な協力関係を築く。
(2)連携する医療機関とは定期的に(年4回以上)院内感染対策に関するカンファレンスを行い、感染対策に関する質の向上を目指す。
患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
(1)当院ホームページに感染対策指針を掲載し、患者又は家族に閲覧できるようにする。
(2)患者・家族等へ疾病の説明とともに、理解を得た上で感染対策に協力を求める。
その他の当該病院等における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
(1)職員は感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、マスクの着用の励行など常に感染予防策の遵守に努める。
(2)職員は、自らが院内感染源とならないよう、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、病院が実施する各種ワクチンの接種に積極的に参加する。
(3)職員は、感染対策マニュアルに沿って個人用防護具の使用、リキャップの禁止、残全装置付き器材の使用、職業感染の防止に努める。


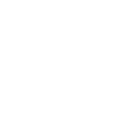 病院案内
病院案内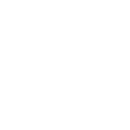 外来案内
外来案内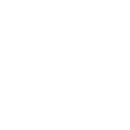 入院案内
入院案内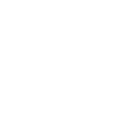 在宅支援
在宅支援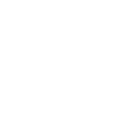 部門案内
部門案内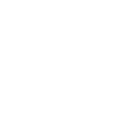 初めての方へ
初めての方へ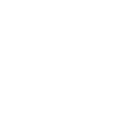 医療機関の皆さまへ
医療機関の皆さまへ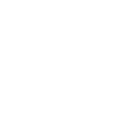 相談窓口
相談窓口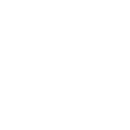 リンク
リンク
